リフレッシュ研修~講義編~の続き。次のテーマは、「日本と世界の違い」。いろいろな国の事例を交えながら紹介してくれた。
日本と世界の違い ~トレーニング編~
講師からまず「日本はサッカーの入り口で何を教えますか?」と問いかけがあった。「日本は「基礎」が大切。ジグザクドリブル、対面パス、リフティング、1対1。ドイツでは見たことない。「基礎」は大事ですよ。ただ、試合で使えるかどうか。蹴り方?蹴れればいい。パスは通ればいい。1対1?実際の試合は?」と。つづけてドイツの例を紹介してくれた。
ドイツの10歳以下は「フニーニョ(3対3)、4ゴール」のトレーニングを取り入れている。それはなぜか?分析すると4ゴールは3人のボールタッチ回数がほぼ同じ。2ゴールはうまい子のボールタッチが極端に多い結果となったそうだ。1人しかうまくならないか全員うまくなるかの違いだとのこと。ゴールの数で各プレーヤのタッチ数が変わるのは驚きであり学びだった。
オランダは、4対4、今はGK+4対4。なぜか?サッカーに必要な幅と深さ、トライアングルが生まれる。3対3ではトライアングルが1つ。4対4になるとトライアングルが4つ生まれる。
ポルトガルは、1対1+2フリーマンなど「フリーマン」をつけることが多いそうだ。「フリーマンがあるところが日本との違い。日本はなかなかフリーマンが出てこない。でてくるのが遅い。フリーマンがいると攻めはいつ、どう使うか?守りはどっちに行くべきか?オンの選手かフリーマンか、判断する要素が出てくる」
そして改めて「日本はなにをやってますか?ドリル練習?1対1?シュート練習?」との投げかけがあった。トレーニングについて「リアリティとクラリティのバランスを意識してますか?」ということだろう。C級ライセンス講義でも習ったことだ。 私自身もできるだけリアリティを持たせたメニューを心掛けている。簡単に言えば、敵・味方がいてゴールがあること、攻撃・守備・切り替えの要素があるように心掛けている。そのうえで、試合で起きた現象を改善したい場合はその部分だけ切り取りトレーニングするといった形だ。試合のためのトレーニングでなければならない。サッカーを始めたばかり、低学年であろうともだ。「サッカーはサッカーでしか上手くならない」ジョゼ・モウリーニョ監督が残した言葉だ。

日本と世界の違い ~環境編~
続いて「日本と世界の環境面の違いについて」。フランスの育成年代は20チームくらいのリーグ戦が38週(約10か月)にわたり行われるとのことだ。トップとほぼ同じだそう。私が子どものころはU-18までリーグ戦など存在せず、トーナメント、カップ戦のみだった気がする。大会が終われば次の大会まで練習と練習試合が続く、そのうえ次の大会までが長かった気がする。今はだいぶ改善してきていると思う。U-12になると長期リーグが4月頃から始まり12月頃まで公式戦がある。U-18も1年を通してリーグ戦があり、成績により昇格・降格もあり、Jリーグと同じようになっている。また、同じクラブ・高校で2チーム以上構成し、なるべくたくさんの子どもたちがプレーできるようにしているところが多く見受けられる。公式戦はほぼ芝(天然芝、人口芝)のグラウンド。環境面はとても進歩していると思う。子どもたちにとって、とてもいいことだと思う。

これから私たちにできること
最後は「これから私たちにできることは?」というテーマだった。おおきく2つで「自主・自立を促すことに取り組む」「子どもが育つには時間が必要」とのこと。
「自主・自立を促すことに取り組む」について、子どもは外発的動機(勝ったらごほうびなど)、内発的動機(もっとうまくなりたい。こういうプレーがしたい)が絡み合って徐々に内的動機に近づいていく。初めから内的動機は難しい。時には外発的動機を取り入れて、子どもたちが自主的に取り組むように促すことが必要。そしてトレーニングで身につけさせたいことができるように仕組み・しかけを取り入れることが大事だと。言うだけではなかなか難しいと。
実技でやった「4色のビブスに色分けしてのボールボゼッション」は「観る・判断する・実行する」のためによく仕掛けられていると思う。鬼でない色を観て判断する必要があるからだ。さらに連続して同じ色はNGという制限をつけることにより、プレーヤーはもっと多くの情報を素早く正確に観て判断しなければならない。これが仕掛けだと思う。
「子どもが育つには時間が必要」について、「促成栽培は失敗する」という言葉があった。急いで育成しても途中で腐って消えていく、上の年代でダメになるケースもある。天狗にさせないことが大事だと。
とても勉強になった研修であった。学んだことを現場で試して効果を観ていきたい。













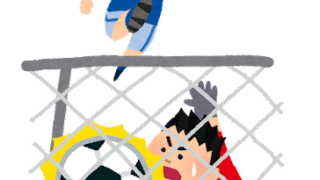






![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3842af66.228fb6dd.3842af67.ea1fdfb0/?me_id=1225050&item_id=10106835&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fballclub%2Fcabinet%2Fclossmall25%2Fmsbf.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
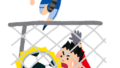

コメント